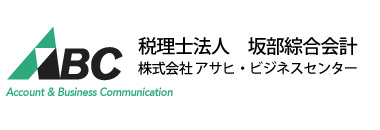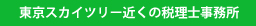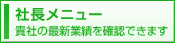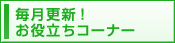会長コラムCOLUMN
第45回 「その年にならなければわからぬこと…」 2019.11.08
「親になってみないと、親のありがたみはわからない。」ああ、こんなに苦労して親は私を育ててくれたのか。
63歳になったばかりの10月に鬼籍に入った父は、町医者の肺炎という診断結果に不信を抱きながも、医師の指示に従って治療に専念した。結局、肺の影は肺がんであった。転院した神奈川の慈恵医大病院の若い医師は、私たち家族に「治療は内科的療法と外科的療法があります。放射線等を使った内科的療法を採用しましょう。」と言った。3日後に見舞いに行くと、医者の方針が変わっていた。「開けましょう(手術しましょう)」。私と兄は、医者の言葉には逆らえないと慰めあった。手術は成功したと告げられたが、合併症で腹水がたまり、1カ月後父はあっさり帰らぬ人となった。
親戚・知人は早すぎる死を悼んだが、私は63歳の死を特段早いと思わなかった。30前半の生意気盛りは、税理士資格を取ったばかりで有頂天になっていたのだと思う。もし私が、身内の経営している税理士事務所を引き継いでいたとすると、そんな気持ちにはなっていなかったであろう。その高慢な鼻っ柱を折ってくれる環境が、自らを省みる機会を与えてくれるははずであった。当時は、将来の不安よりも、こうしてやろう、ああしてやろうという妄想(夢?)が先に立っていた。その時分に、密かに座右の銘にしていたのは、「人間(じんかん)50年、下天(げてん)のうちをくらぶれば夢幻(ゆめまぼろし)の如くなり」という織田信長が好んで舞ったという敦盛の一節であった。やはり私は、父親の死を特段早いと思えなかった。
父親の年齢を超えてみて、目は衰え、歯はこぼれ、体は思うように動かないと感じるようになった。そして、あることに気づく。自分が主体だ、自分の人生は自分で生きるしかない。逆説的にいうと他人の人生を自分は生きることはできない。それは、親であっても子であっても同じだ。私は、父の人生を生きられるわけではない。
「親になってみないと、親のありがたみはわからない。」私は、親がこんな思いをして私を育ててくれたという強い実感を持てない。ただ、この世に比類のない(2人といない)私を送り出してくれたことには強い感謝の念はある。魚屋から始まった商売で稼いだ金でもって、今の税理士の私はある。
体は衰えていって末期を迎えるにしても、私の意識は、そう衰えるものではないと感じている。父親も病院にかかる前はそう思っていたに違いない。そうやって時空をこえた意識の交錯が「その年になってみないとわからない」の本当の意味だと思う。